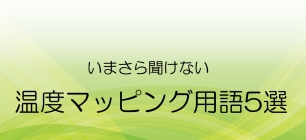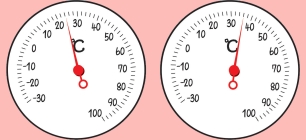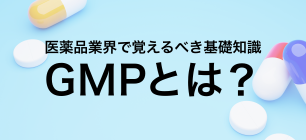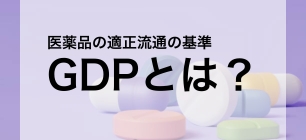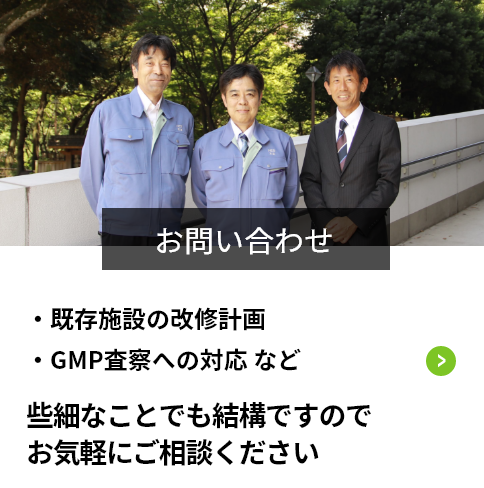医薬品製造における交叉汚染――そのリスクと現場での実践的な対策
医薬品製造の現場では、日々さまざまな原料物質を取り扱っています。一見いつも通りの作業のように見えても、気を抜くと大きなリスクにつながるのが「交叉汚染(クロスコンタミネーション)」です。製品に別の成分が混入してしまうことで、品質や安全性が損なわれるだけでなく患者さんの健康にも影響を及ぼす恐れがあります。特にホルモン剤や抗がん剤など高薬理活性のある医薬品を扱う現場では、作業員の安全確保という意味でも細心の注意が求められます。
例えば、作業員が無意識に他の部屋へ原料物質を持ち込んでしまったり、共用設備に微量の成分が残っていたりと、気付かない形での混入リスクは想像以上に多いのです。今回はそうした交叉汚染を防ぐために現場で実際に行われている具体的な取り組みをご紹介します。
設備の専用化と共用設備の管理
交叉汚染リスクの高い製品、例えばホルモン剤や抗がん剤などを製造する場合は、製品専用のライン・作業室の設置が推奨されます。これにより製品同士が物理的に接触することを防ぎます。
共用設備を用いる必要がある場合には、製品を毒性や感作性などの性質によってグループ化し、使用順序や洗浄の厳しさを調整する「製品グループ化管理」が有効です。例えば、リスクの低い製品から高い製品へ順番に製造し、洗浄バリデーションを実施して次の製品に移るといった対応が一般的です。
洗浄バリデーションの徹底
共用設備では、前製品の残留物が次製品に混入しないように科学的根拠に基づく洗浄バリデーションが必要です。例えば、錠剤の打錠機では細かな隙間に粉体が残留することがあるため、分解洗浄を行い残留確認試験(スワブテスト、TOC測定など)を実施します。製品ごとの許容残留量(MACO)を算出し、それを基に洗浄の有効性を評価します。高活性物質の場合には、洗浄後でも封じ込め設備を使用した再確認が行われることもあります。
作業員の教育と動線管理
作業エリアの移動時にリスクが生じないよう動線を工夫することも重要です。例えば、作業員が異なる製品エリアを行き来する際には、作業着の色分けや、エリアごとの専用作業着の使用といったルールを設けることで、交叉汚染のリスクを低減できます。また、スティッキーマットやエアシャワー、ゾーニングによるエリア分離も有効です。
作業員は日々の業務の中で交叉汚染のリスクを最も近くで接する存在であるため、教育は形式的な研修にとどまらず具体的な事例や現場での判断力を養う内容が求められます。実際のトラブル事例を共有したりグループディスカッションやロールプレイングを取り入れることで、知識の定着だけでなく意識の向上にもつながります。教育の質が現場力に直結することを意識し、継続的な教育体制を構築することが不可欠です。これは新人教育だけでなく、既存作業員への定期的なリフレッシュ教育や、GMP改正・製造手順変更時のタイムリーなフォローアップも重要です。
空調システムの最適化
空調設計においては、粉体の移動を最小限に抑えるために、まず発塵源の近くで直接吸引できるようなHEPAフィルター付き局所排気設備やダストコレクターの導入が有効です。また、静電気による原料物質の付着を防ぐために帯電防止床材を使ったり、適切な湿度管理を行うことも重要です。さらに、施設全体でエリア間およびグレード間の差圧をどのように構成するかを綿密に計画する必要があります。空調の設計は単に目標となる数値を達成することだけが目的ではなく、実際の運用や日々のメンテナンスを見据えた、現場で無理なく機能する現実的なプランであることが求められます。
平原エンジニアリングサービスでは、多くの医薬品製造施設で培った知見とノウハウをもとに、無理なく持続可能な空調システムの構築をサポートいたします。
リスクベースアプローチの導入
近年、医薬品製造における品質リスクマネジメントの重要性が高まっています。特に、2006年にICH Q9ガイドラインが制定され、リスクマネジメント手法の適用が強く推奨されるようになりました。
リスクベースアプローチでは、製品の特性、患者の曝露リスク、生産頻度、毒性レベルなどを総合的に評価し、必要な対策の優先順位を決定します。すべての工程に一律に過剰な対策を講じるのではなく、リスクの大きさに応じてリソースを合理的に配分することが求められています。例えば、高薬理活性物質を共用設備で製造する場合には、封じ込めシステムの導入、洗浄バリデーションの強化、健康リスク評価に基づく限界値設定などが不可欠となります。一方、年間数回の生産で毒性も低い製品であれば、簡素な清掃手順で対応できるケースもあります。
ISPE(国際製薬技術協会)は、ICH Q9をベースにした「Risk-Based Manufacture of Pharmaceutical Products(Risk MaPP)」というガイドラインを発行しており、2021年にはその第2版がリリースされています。第2版では、より明確で実践的なリスク評価手法や封じ込めおよび洗浄に関する管理戦略の考え方が強化されており、現場での運用に直結する具体的な指針が示されています。さらに、2021年に改正されたGMP省令では、薬理学的・毒性学的評価に基づく科学的根拠のある交叉汚染防止策の導入が義務化されました。これにより従来の“ハザードベース”の考え方から“リスクベース”のアプローチへと、本格的な転換が求められています。
このように、リスクベースアプローチの導入は、品質確保だけでなくコスト効率と作業安全性の両立にもつながる重要な取り組みです。各製造現場において、自社の状況に合った最適なバランスを見出すことがこれからの品質管理には欠かせません。

専門家の支援による最適な対策構築
交叉汚染対策を確実に進めるためには、現場の状況を正しく捉え、実効性のある改善策を導き出す力が求められます。平原エンジニアリングサービスでは、GMPに精通したエンジニアが現地調査や作業動線の分析を行い、貴社の製造環境に最適なソリューションをご提案いたします。例えば、空調設計の見直しやゾーニングの再構築、設備配置の最適化など、現場ごとに異なる課題に対して柔軟に対応し、交叉汚染リスクの根本的な低減を実現します。洗浄バリデーションの支援や文書作成のサポートも可能です。
「どこから手をつけてよいか分からない」「すでに対策をしているが、本当に十分か不安」——そんなお悩みに対して、平原エンジニアリングサービスの技術と経験が力になります。ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
昨今、ジェネリック医薬品メーカーにおける製造不正や品質問題が相次ぎ、業界全体の信頼性が問われています。中には適切な交叉汚染対策が取られていなかったことが発端となり製品の自主回収や行政指導にまで発展したケースもありました。
交叉汚染は製造現場での“ちょっとしたこと”が企業の存続を揺るがす大きなトラブルに繋がることもあります。だからこそ日々の業務の中で基本をしっかり守ることが最も効果的なリスク対策です。目に見えにくいからこそ見逃しやすい交叉汚染です。現場で働くひとりひとりがそのリスクを正しく理解し確実に対応していくことで、安全で信頼性の高い製品づくりを支えていきましょう。